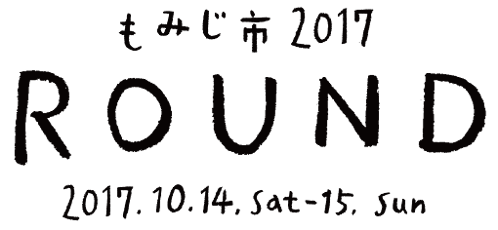【成城・城田工房プロフィール】
もみじ市当日、初秋の河川敷に咲き乱れる花と見紛うばかりにそこかしこにあふれる渦巻き状のソーセージ、その名も“うずまきちゃん”。狛江が誇る自家製パストラミの名店「成城・城田工房」が確かな技術と最高の素材でていねいに創り上げたそれは、見た目の華やかさとは裏腹に、じつに寡黙で誠実で、だからこそギミックなしにおいしくて。「おいしいは正義」とは誰が嘯いたか、だがこの圧倒的なまでのおいしさへの勤勉さの前に、どこか真を射抜いているようにすら思える。そしてそれは決してどこにでもあるおいしさ、ではない。あたりまえに咲く花などないように。
http://seijohamu.com
【商品カタログ予習帳】

『うずまきちゃん』
(画像はポーク。もみじ市当日は黒胡椒・あらびき・トマト&バジルの三種類を炭火焼きした三連串となる予定)
【スペシャルインタビュー「ハムに捧ぐ、強い気持ち・強い愛」】
裏表のない軽快な語り口の奥に静かに宿る、ものづくりへの強いストイシズム。それはいつだって、彼が創り出すソーセージそのものとどこか似ている。ぐるりと渦巻かれた意匠はどこまでもポップでありながら、味わいの奥行きがあくまでも実直でまっすぐなのだ。これからもずっと続いていくだろうこの道の先にあるパストラミたちの、彼が見るあるべき姿をのぞき込んでみたいと思った。
独立するとき、ほんとうに風が吹いた
東京農大在学中、収穫祭のために徹夜で作ったハムがきっかけとなり、「ハム屋になる」と決意。独立して自分の店を持つまでのストーリーをすでにこの時点で明確に描いていた、というのだから驚かされる。
「いわゆる街の喫茶店だった実家のコーヒーやピラフと、手造りハムの単価の違いにまずびっくりして(笑)。もちろんハム作り自体も楽しいんだけど、ちょうど就職難だったし『文化祭でハム作ったからハム屋になりたい』、採用するほうもわかりやすいでしょ?(笑)。イメージも、最初は企業に入って、だんだん規模を小さくしていって、最後は自分で、っていうのがぼんやりとあって。で、まずは鎌倉の会社にお世話になりつつ、『将来は独立する』って周りに話してたら、8年目でほんとうに声がかかって」
飛び込んできたのは、日系ブラジル人が営む豊橋のハム屋の工場長のポジション。あまりの文化の違いに戸惑うも、現在のスタイルに導いてくれた“うずまきちゃん”の師匠と出逢い、それが大きな転機となる。
「働いている子たちはみんなブラジル人なんだけど、日本と国民性が違うので、あまり仕事熱心な感じではなくて。『城田はどうしてそんなに仕事したがる?』みたいな(笑)。でもこっちは日本企業で叩き込まれてるから、段取り組んでガンガン効率よくやりたいし。当然まったく噛み合わなくなって、心が半分壊れてきて(笑)。途方に暮れていたときに、そのハム屋が浜松の工場を間借りすることになって、そこの社長の仕事を手伝うことになって。曰く『店で売るだけじゃ生きていけないから、どんどんイベントに出なさい』と。行けばコンサートやお祭りで、彼が考えた“くるくるウインナー”が飛ぶように売れるわけ。店舗と催事、両輪で回して安定させるっていうビジネスのコツまで教わって。そのあたりで修行のゴールもだいたい見えて、最後は錦糸町の会社で仕上げさせてもらって。そのとき、ほんとうに風が吹いたんだよね。ブラジルハム屋が機械を一新することになって、癖を知り尽くした一式が輸送費だけで手に入る、と。で、いよいよ自分の店を開けて三日目に狛江の夏祭りに出たら、そこに手紙社さんが出店してて(笑)」
いい大人が二日間にすべてを注ぎ込むのがもみじ市。ほんとうに命がけよ(笑)
はたして約束の地にたどりついた「成城・城田工房」。2008年から足掛け9年、大切にしていることは何一つ変わらない。ただただ、素材に誠実であることだけ。もちろん、それが調布の河川敷だったとしても。
「すべてが手探りだから、見渡したらこういう景色になってた、っていう。長嶋監督(巨人軍終身名誉監督)みたいなノリだからさ。『はいこっちー!』『次あっちー!』みたいな(笑)。だから、かっこいい理念みたいなものは別になくて。ただ作るものに関してだけは、手を抜かずに、お客さんを裏切らないようにきちんと作っていれば、味もまたぜったいに裏切らないから。ま、そんな感じだから、作られる量は自然と決まってくるよね。もみじ市でも正直なところ、マックスまで来ていて(笑)。なのに不思議なことに、後先考えずに作られるだけ作っちゃうのよ。“うずまきちゃん”だけで店の冷蔵庫がいっぱいになるのに。賞味期限もあるのに。だけど冷凍したくないのに。そもそも雨降るかもしれないのに。なにかあったら首吊るしかないかも、ってところまでいつも追い詰められる(笑)。それがわかってて、いい大人が二日間にすべてを注ぎ込むわけ。ほんとうに命がけよ(笑)」
同じようにギリギリの紙一重の戦いをしている人たちと同じ場所に立てる幸せ
「ピリピリするし、家族にも悪いなあとは思うけれど」なんて苦笑いしながら、だがどこか照れたようなその横顔はむしろうれしそうでもあって。
「目が三角になるくらいキツいけど(笑)、やりたかったことができているわけだから、毎日すごく楽しいんだよね。で、もみじ市の他の出店者さんたちも同じようにギリギリの紙一重の戦いをしている人ばかりじゃん? そういう人たちと同じ場所に立てて、エネルギーをもらえることをとても幸せなことだと思う。そんな自分にとっての<ROUND>のイメージは「一周」、原点回帰。いつもどおりじっくり作って、食べてもらおうと。新しい世代の作家さんたちも増えてきたけど、まだまだ負けられないし、切磋琢磨したいからね」
もみじ市が年にたった一度だけ、世代を超えた表現者たちをあの河川敷で迎えることになにか意味があるとするならば。ただ表現の向こう側にある生命の確かな輝きを信じることでしか生きられない、かくも気高く美しき魂たちを共振させること、にあるのかもしれない。
〜取材を終えて〜
こんなにもエピソードを捨ててコンパクトに編集するのが困難だった取材はひさしぶり、だったかもしれない。それほどまでにいつもの調子でざっくばらんに(つまり、あまり書けない・笑)ユーモアたっぷりに語ってくれた城田さん。自身の生き様を痛快に笑い飛ばしながら話すその姿に、本気で人生と向き合い、サヴァイヴしてきたからこそ見せられる大人のタフさを感じたのは、きっと気のせいじゃないはず。(手紙社 藤井道郎)