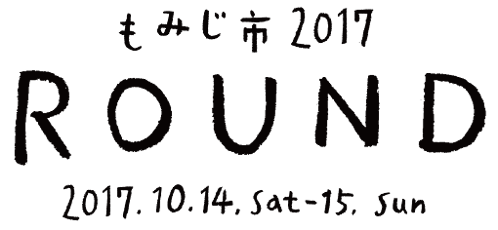【キノ・イグルー プロフィール】
日本中のカフェや雑貨屋、書店、ブーランジェリー、美術館などのさまざまな空間を、世界各国の映画を上映しながら演出してゆく移動映画館、「キノ・イグルー」。120年におよぶ映画史をくまなく紐解ける博覧強記なまでの映画愛が屋台骨にありつつ、どこか彼らのディレクションがいわゆるシネフィル(フランス語で映画通、映画狂)のそれとは一線を画すのは、映画そのものに対する論説ではなく、彼らがどこか映画との出逢い方をこそ慈しんでいるから、ではなかろうか。誰と、どこで、どんなふうに――つまり、映画と出逢うこととは、人生の愉しみそのものなのだと。
http://kinoiglu.com
【商品カタログ予習帳】

年に一度、多摩川河川敷だけにあらわれる『テントえいがかん』

テントの前には、『みんなの好きな映画』ボード

大人も子どもも、テントの中のスクリーンに釘付け
【スペシャルインタビュー「ニュー・シネマ・ライフ・イズ・ビューティフル」】
有坂塁さんと渡辺順也さんによる「キノ・イグルー」があなたのもとに運んでくるのは、ライフスタイルをちょっとだけ洗練させる気の利いた小道具としての映画、ではない。映画という装置を通じて誰だって世界と繋がれると信じさせてくれる、じつにエスプリの利いた力強い“生”へのエールだ。映画の持つ無限のポテンシャルを信じて止まない有坂氏の放つ言葉たちの奥には、そう断言させるだけの確かな熱、があった。
いい映画を観ると、観終わったあとって余韻が残るじゃないですか。それって、どう面白かった、って言葉で説明できないから余韻が残る、と思っていて
ところが信じがたいことに、氏は19歳になるまでむしろ映画は大嫌いだった、というのである。それも、こともあろうに娯楽映画の永久欠番、スピルバーグのタイトルが理由で。
「子どものころ『グーニーズ』(85年・米)は感動したものの、『E.T.』(82年・米)を観てなぜか映画が嫌いになって(笑)、それから12年間1本も観ず、無理やり連れて行かれた映画館で『クール・ランニング』(94年・米)を観たんですけど(笑)、席に着いた瞬間、すごく落ち着く場所だな、と思ったんです。双子の兄がいるんで、つねに人から見られてるって意識が強かったんですけど、暗くなって一人になれるのに、孤独じゃないっていう。でもそう意識したのはずっとあとの話で、答えがわからないから夢中になったんでしょうね。そこではっきりスイッチが入ったし、おさえられなかった。恋といっしょですよ。人を好きになっちゃう理由なんてわからないじゃないですか? あの感覚にほんとうに近くて」
なるほど映画の筋書きを追う歓びもさることながら、その生い立ちと、魂の開放とすらいえる映画体験を鑑みれば、現在の「キノ・イグルー」のスタイルにも大いに合点がいく。特定のジャンルやタイトルというより、映画という体験そのものを楽しんでもらいたい、そんな初期衝動にも似た無垢なイノセンスが彼らを今の場所へ導いたのだ。
「でも最初はどうすればいいか、ずっとわからないままだったんですよね。いろんな人といろんな映画を観てコミュニケーションしていくうちに削ぎ落とされて、シンプルに人と場所と映画を言葉にならないような感覚でつなげる、体験してもらうっていうところに行き着いて。そこからしか見えない風景がやっぱりあるんですよね。いい映画を観ると、観終わったあとって余韻が残るじゃないですか。それって、どう面白かった、って言葉で説明できないから余韻が残る、と思っていて。そもそもそういうものだと。もちろん作品を一つの芸術として分析するのも面白いし、読みはしますけど、広がりがないんですよね。答えらしきものとして、すでにそこに言葉として存在してしまうから。それよりは誰かの映画体験を聴くほうが、よっぽど映画が観たくなるわけで。たとえば中学のときにWデートで映画を観に行った友だちが男子二人で『ダイ・ハード』(88年・米)を選んだら、女子二人が超引いてた、とか(笑)」
肩書なんて、一発で取れますよね。そんな奇跡が起こせるのが、映画のポテンシャルなんです
ユーモアに溢れるエピソードを引きつつも、彼は気づいているのだ。心が通じる瞬間のコミュニケーションとは、とてもシンプルだということ。そして、そうすることでしか血は通わない、ということに。
「たとえ映画祭のような大きな企画であっても、映画を通してそこにいるすべての人とコミュニケーションを取ってもらいたいんです。映画好きって、まわりに同好の士がいなくて一人で楽しんでいる人も意外に多いんで、そういう人たちが安心して映画の話ができる天国を創りたかった。芝公園でやったときは、そこにいる全員に自分の好きな映画を書いたネームプレートをつけてもらって。スタッフも、重役さんも、制服を着た警備員さんも。そしたらその警備員さん、まったく似合わないんだけど『ラブ・アクチュアリー』(04年・英)って書いてて(笑)。肩書なんて、一発で取れますよね。そんな奇跡が起こせるのが、映画のポテンシャルなんです」
縛られすぎると、その場所でしか創り得ない空気から離れてしまうことを懸念して、毎年あえてもみじ市のテーマをそこまで意識せずに参加してくれている彼ら。とはいえ、「キノ・イグルー」の日々の活動でも「もみじ市でしか使わない」というテントえいがかんへの想いは、こちらが恐縮するほどに強い。
「もみじ市に最初に出るときに作ったテントなんですけど、あの河川敷の風景にフィットしすぎていて、もみじ市以外では使いたくなくて。だからもみじ市は、そのテントえいがかんがオープンする場所、に尽きるんです。もちろん上映するものは毎年すこしずつ変わるんですけど、あくまでこの場所でこの時間にこのテントのなかで15人で声出して笑って、『暑い!』といいながらテントを飛び出して、『涼しい!』っていう(笑)、あの一体感。自分たちの言葉と声で映画を届けて、それをふくめて空気を作るので、毎回ライヴだし、一年間積み上げてきたものを出すかけがえのない場所であって」
映画史における芸術としての120年の長短は別の機に論を譲るが、彼らはここもみじ市で自らドラスティックにその可能性を切り開こうとしている。だからなのだろう、テントえいがかんでは映画が始まるブザーは鳴らされない。まだ始まってすらいない、とばかりに。
〜取材を終えて〜
「キノ・イグルー」では、取材を受けるのはスポークスマンである有坂さん一人。曰く、「よく一人でいいじゃん、っていわれるんですけど、ぼくのなかでは二人じゃなきゃ絶対に駄目で。いっしょに会場にいて、終わったあと二人で帰ってちょっと呑んでこそ、まだ醒めてない気持ちの盛り上がりを共有できるから」。二人で「キノ・イグルー」であることは、それこそが彼にとっての映画体験そのもの、なのかもしれない。(手紙社 藤井道郎)