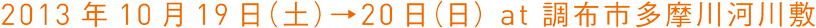五月女寛さんは旅人のような人だ。
個展や企画展で日本各地に出かけては、ギャラリーのオーナー、その地域で創作活動をしている作家、その友人が営むおいしいお店…といった具合に、人から人へと交流の輪を広げ、たちまちその土地に溶け込んでしまう。五月女さんがいつも肩に掛けている大きなカバンにはスケッチブックと絵の具が入っていて、旅先で美しい風景に出会うと、写真を撮るのではなく絵に残すという。初めて出会った人や、場所や、風景にも、ずっと昔からの友人のように温かく接することができる人。それが、わたしの五月女さんの第一印象だ。
陶芸家・五月女寛さんは、もみじ市になくなてはならない作り手の一人だ。2009年のもみじ市からずっと、小さく愛らしい「家」の形のオブジェを中心に、マットな質感と優しい色の作品で会場を彩ってくれている。手のひらにのるほどの愛らしい家がずらりと並ぶ光景は、まるで小さな町が現れたようで、そこに流れる時間や物語を空想せずにいられない。
小さな家は、よく見ると一つひとつ色や形が違い、それぞれに表情がある。のっぽの家、斜めの家、古びた家、赤・青・黄色の家…。どれもシンプルなフォルムだけれど、時を経たような色や質感を表現するのに、五月女さんは惜しみなく手をかける。例えば、輪郭に錆びたような色がのぞく家は、赤土の上に化粧土を施した後、辺を削って下地をわずかに見せている。表面に細かなヒビが入った花入れは、化粧土の乾燥によって生じるヒビの表情を生かしたものだ。それらは決して強く主張することはないけれど、窓辺やテーブルの片隅に置くと、日常の風景が静かで優しい光を宿す。五月女さんは言う。
「使う人の暮らしの中で、初めて完成するような作品を作りたいと思っているんです。窓辺に置いた小さな家が、窓の外の空を背景に一つの絵になるような。花器に生ける花をわざわざ買わなくても、道ばたで見つけた花の方が似合うような」
そう言って屈託のない笑顔で笑う五月女さんのまなざしは、オブジェや花器を買ってくれた人の「帰る家」へと向けられている。オブジェは、ともすれば「嗜好品」として、暮らしとは遠い位置に置かれることもある。だけど、五月女さんの見つめる先は、家族が「おはよう」「おやすみ」と言葉を交わす暮らしの中に、自分の作るものが溶け込む風景だ。
「なぜ、”家”を作るんですか?」
わたしのその問いに、五月女さんは少し考えてこう答えた。
「家って、世界中どこの国でも同じような形をしているからかもしれませんね。中に人が住まう空間があって、雨をしのぎ、地面へと流してくれる屋根があって、なんだか安心する。そんな形」
その言葉を聞いたとき、わたしは、五月女さんを旅人のような人だと感じた理由がわかった気がした。旅人には、帰る場所があるのだ。日常を離れて、見知らぬ土地の人々や風景に感動しても、心が帰り着く温かな「家」。言葉が通じなくても、文化が違っても、三角屋根の四角い形を見れば、誰もが自分の帰る家を思い出す。五月女さんの作る家は、わたしたちの心の真ん中にある「家」そのものだ。
今年も、多摩川河川敷に小さな家々が並ぶ町が現れます。その中には、記憶の片隅でいつも自分を待っていてくれたような家が、必ずある。帰ったら家族に見せたくなるような、素敵な花入れやアクセサリーも並びます。お気に入りの作品を見つけて、「ただいま」と笑顔でおうちに帰ってくださいね。
【五月女寛さんに聞きました】
Q1 もみじ市に来てくれるお客様に向けて自己紹介をお願いします。
のどかで猫がたくさんいる雑司が谷に暮らしながら、日々陶のオブジェや花入れを作っています。
Q2 今回のテーマは「カラフル」ですが、あなたは何色ですか?
うーん、黄緑でしょうか。
Q3 今回はどんな作品をご用意してくれていますか? また「カラフル」というテーマに合わせた作品、演出などがあれば教えてください。
カラフルな家、積土などはもちろん、カラフルな紅葉が楽しめる野草盆栽などもご用意いたします。新作の家にはカラフルな旗がのってますよ。
Q4 ご来場くださる皆さんにメッセージをお願いします!
さて、続いてご紹介するのは、ご夫婦で営むパンと器のお店。新たな一歩を踏み出した二人がもみじ市に帰ってきます。
文●増田 知沙