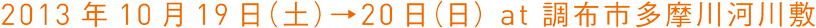パンが“生きている”。
それは、生まれて初めての体験だった。取材前、その店のテラスでかじったパンは、「モモ酵母の食パン」。力強くつながれた小麦をちぎるように食み、噛むごとにぷつぷつと細かく弾けるような食感は、まるで生命を体に取り込むような野性的な感覚だ。それでいて、桃特有のふわりとした甘い香りに心は安らぎ、後を引く酸味に惹かれるようにまたひと口、さらにひと口と続く。この店のパンは、明らかに自分が食べてきたパンとは異なる。これからこのパンのつくり手と話せる、そう思うと胸が高鳴った。
さいたま市浦和区、住宅街の小道を歩いていく。ここらへんかな、そんな予想が何度も外れながら、ようやく目的地となる場所に着いた。「畑のコウボパン タロー屋」。自家菜園から採れる季節の果物・野菜・花から酵母を育て、四季折々のパンを作っている。取材に訪れた土曜日は、今春オープンした新店舗の窓口販売の日。週に二日だけの販売だが、日によっては開店前から列ができ、一時間ほどで売り切れてしまうそう。貴重な営業日、しばらくお店の様子を後ろから見てみることにした。
近所に住むちいさな男の子。千円札をぎゅっとにぎりしめていた。いつもお使いに来るそう。たしかに慣れた感じだ。「何のパンが好き?」と聞くと、「しょっぱいパンが好き」と答えてくれた。
続々とお客さんが来る。こちらの方は、「やわらかくて食べやすいパンがいいわ」とスタッフの方にリクエスト。おすすめに従い「巨峰酵母のデザートフォカッチャ」と「モモ酵母の白パン」を購入。スタッフの方が、保存の仕方やおいしい召し上がり方も丁寧に教えている。
「汚れちゃうから靴脱ぐね」と店に入ってきたのは、近くの畑で作業を終えた農家さん。大きな「巨峰酵母のノア・レザン」を男らしく買っていった。説明をしているのは、店主の橋口太郎さん。
「動きがよくない」と橋口さんが話すこの日も、取材を始めて少しすると店頭用のパンは売り切れとなった。お店が落ち着いて来たので、テラスのベンチでゆっくりとお話を伺うことにした。
店主の橋口さんは、専門学校でインテリアデザインを学び、店舗設計の仕事をした後、友人とデザイン事務所を立ち上げて、2年間ほど紙媒体のデザインをしていたという。自分が抱いていたクリエイティブなイメージと異なり、実際は受け身な仕事が多く、そのギャップが高まってきたある日、知人から酵母の話を聞く。自分でも酵母を起こせるということに興味がわき、試しに、庭に成っていたびわで酵母を起こしてみた。
「水に入れて管理するだけで、しゅわしゅわと泡が出て、酵母液が出来る。まるで“魔法”のような体験でした。それから色んな酵母を起こすようになりました。家中に酵母液のビンが転がっていて、まわりにはびっくりされましたね。酵母でパンを作り始めるようになり、実家の畑でも、酵母のために野菜や果物を育て始めました。既存の社会の枠組みにあるものを仕入れなくても、ものが生み出せる。そんな酵母中心の生活には毎日新しい発見や喜びがあって、楽しくて、それがあるからこそ、今パンをつくらせていただいていると思います」
タロー屋さんのパンづくりの入り口は、自然酵母にある。こんなパンがつくりたいから、それに合わせた酵母をつくる、という考え方ではない。起こした酵母の味を確かめ、それに合ったパンを生み出すのだ。初めは副材料を入れるのがこわかった、という。今も酵母の風味を損なわないよう、合わせる素材には気をつけている。これまで酵母といえば、どちらかというと食感を形づくるものかと考えていた自分にとって、酵母由来の香りがわっと広がるタロー屋のパンは驚くべきものだった。
「酵母はたしかにパンを膨らますことに使われますが、単なる膨らましの材料としては考えたくありません。それでは“つくる楽しみ”が薄れてしまう。たとえば、レーズンなどのドライフルーツは甘みが強く、発酵しやすい優秀な酵母です。パンを膨らませる目的だけ考えれば、この酵母だけあれば良い。だけど、さまざまな酵母を起こした時の喜びは、何ものにも代えがたい。それを皆さんにも感じて欲しい。フレッシュな酵母でつくられた季節感のあるパンを皆さんに味わってほしいのです」
橋口さんがつくる酵母の数は、年間約50種類。1種類の酵母を長年つないで使うパン屋さんもある一方で、タロー屋のパンは季節の素材と「一期一会」だ。
「今も金木犀の開花が遅れていてドキドキしているんですが、必ずしも上手く手に入るとは限らない自然の素材と誠実に向き合うのは、緊張感のいる作業です。気候の変化で素材を使える時期がずれたり、パンを発酵させるために温度や湿度を管理する機器を使っても、外的変化で左右されることもある。ですが、それはつくり手にとって必要な緊張感。釣りをするのが好きなんですが、もしかすると釣りとパンづくりは似ているかもしれません。タイミングを“待つ”こと。酵母の発酵、パンの発酵のタイミングを見誤らず、世話をすることが上手くできた時、おいしいパンができる気がします」
春は、八重桜の若葉で起こした酵母。夏は、ラベンダー酵母。秋は、初めて花でつくった金木犀酵母。冬は、柑橘系やイチゴの酵母。四季の移ろいとともに咲く花が変わるように、つくられる酵母の変化とともに店に並ぶパンも変わる。毎年春の季節だけ来るお客さんもいるそうだ。今年もこの季節になりましたね、と挨拶をするのが橋口さんの楽しみらしい。
今でこそ工房での窓口販売を行っているが、昔は卸販売だけだったというタロー屋。直売を始めたきっかけを尋ねてみた。
「前の工房で卸し用のパンを焼いていると、香りが外に流れていくんです。近くの中学校の通学路にあって、ある中学生の子が『パン屋さん、いつから始まるんですか』と毎日のように手紙を入れてくれて。近所の方々からの声もあり、テーブルにクロスをかけてその上にちょんちょんとパンを置いた、バナナの叩き売りのような状態でお店が始まりました」
そんなエピソードを聞きながら、タロー屋にとって、訪れてくれるお客さまは特に大切な存在なのだろう、と取材前の店の様子を思い返していた。お客さまが外に見えると、「2週間ぶりに来たね」「あの人がいつも買うパン、まだ残ってるかな」と話すスタッフの皆さん。馴染みではない方にもパンの好みを伺ったりと、パンを通して会話が生まれていた。
「僕はパン屋ですが、パン職人と言われると違和感があります。パンをつくりたい、というだけではなく、パンはお客さんと自分がコミュニケーションをとるための媒介のようなもので、“人とつながりたい”という思いがどこかにあるのかもしれません。パンを通して、ここでお客さんとつながることが実はいちばん楽しい。なにより喜びを感じていると思います」
四季折々のフレッシュな素材、そしてそこから生まれるパンを口にする人々。タロー屋にとって、それぞれとの出会いはかけがえのないものだ。
取材を終えて5日後。タロー屋のホームページを開くと、ボウルいっぱいの色鮮やかな金木犀の写真が、トップページに載っていた。秋色のパンが、もみじ市にやってくる。
【畑のコウボパン タロー屋 橋口太郎さんに聞きました】
Q1 もみじ市に来てくれるお客様に向けて自己紹介をお願いします。
さいたま市浦和区の小さなパン工房「畑のコウボパン タロー屋」と申します。四季折々の果物、お野菜、花から酵母を起こしてパンを焼いています。
Q2 今回のテーマは「カラフル」ですが、あなたは何色ですか?
店先に並ぶ酵母瓶の色にならえば、いまの季節は金木犀のオレンジ色の気分です。
Q3 今回はどんな作品をご用意してくれていますか? また「カラフル」というテーマに合わせた作品、演出などがあれば教えてください。
秋の酵母で作るカンパーニュ、フォカッチャなどなど、生命力を感じられるような、元気なパンをたくさん焼き上げて参りたいと思います。金木犀のお花も無事に収穫出来たので、花酵母のパンもご用意したいと思います。噛んで味わい、のど越しに抜ける風味から秋色を感じる…そんなパンをお作りしたいです!
Q4 ご来場くださる皆さんにメッセージをお願いします!
さて、続いてご紹介するのは、人呼んで“ミスタークラシックカメラ”。フィルムカメラ専門店を営むあの方の登場です!
文●柿本康治